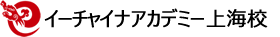中国語には日本語には存在しない、あるいは区別が曖昧な子音が多く存在します。これらの子音の習得は、日本人学習者にとって大きな課題となります。
有気音と無気音の区別とその重要性
中国語の塞音(b, p, d, t, g, k)や塞擦音(j, q, zh, ch, z, c)には、息の吐き出しを伴う「有気音」と伴わない「無気音」の区別があります 。日本語の清音は一般的に無気音に近い傾向があるため、日本人学習者は中国語の有気音を発音する際に、日本語の清音と同じように息を強く出さずに発音してしまう傾向があります 。この区別は、中国語においては意味を区別する重要な要素であり、例えば「b」と「p」のように、有気か無気かで意味が全く異なる単語が多数存在します。
そり舌音(zh, ch, sh, r)と舌尖前音(z, c, s)の混同
そり舌音(zh, ch, sh, r)は、舌を上向きに反らせて発音する音で、日本語にはこの種の音が存在しないため、日本人学習者にとって特に習得が難しい発音です 。多くの日本人学習者は、そり舌音を舌尖前音(z, c, s)と同じように、舌を反らせずに発音してしまう傾向があります。例えば、「zhi」を「zi」のように「ズー」と発音したり、「shi」を「si」のように「スー」と発音したりすることがよく見られます 。
ただし、台湾や中国南部の方言では、そり舌音を舌尖前音と同じように発音する傾向があるため、これらの地域では日本人学習者にとって発音の負担が少ないと感じられることがあります 。しかし、標準中国語(北方方言)においては、これらの音の明確な区別が不可欠であり、正確なコミュニケーションのためには習得が求められます。特に「ri」の発音は、日本語のラ行音(特に「リ」)がそり舌に近い舌の動きをするため、比較的発音しやすいと感じる学習者もいますが、中国語の「e」と組み合わせた「rè」(熱)のような単語では、その発音が非常に難しいとされています 。
特定の摩擦音(f, h)の発音課題
中国語の摩擦音である f [f](唇と歯を使う唇歯清擦音)と h [x](舌の根元を使う舌根清擦音)も、日本人学習者にとって課題となることがあります。日本語の「ふ」の音は [ɸ](両唇を使う双唇清擦音)であり、中国語の f とは発音方法が異なります。また、日本語には舌根摩擦音がないため、h の発音も日本語の「ハ行」とは異なる、喉の奥をこするような音を出す必要があります 。
子音優先の発音意識の欠如
日本語が「母音優先」の言語であるのに対し、中国語は「子音優先」の言語であるという根本的な違いがあります 。日本語では、ほとんどの子音は母音と一体となって「一瞬の小爆発」のように短く発音される傾向があります。例えば、「カ」の「k」の音は非常に短く、すぐに母音の「ア」に続きます。しかし中国語では、子音は音節の「土台」として、より長く、独立して発音される必要があります 。
日本人学習者がこの子音優先の意識を持たないまま発音すると、子音の持続時間が短くなり、必要な送気(有気音)や正確な舌の位置(そり舌音など)が十分に形成されません。これは、単に「日本語にない音」を模倣するだけでなく、日本語の音節構造における「子音の役割」の根本的な違いを理解していないことに起因します。この理解の欠如が、発音の曖昧さや誤解につながり、中国語の音韻的意味の区別を困難にさせます。効果的な矯正には、個々の音の生成だけでなく、音節内での子音の「準備」と「解放」のフェーズをより意識的に行うよう、学習者の発声器官の動きを再構築することが求められます。