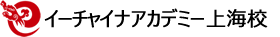上海人の朝ごはん文化は、伝統と革新が共存する興味深い側面を持っています。その代表例が「四大金剛」と呼ばれる伝統的な朝食メニュー——焼き餅(大餅)、揚げパン(油条)、もち米団子(粢飯)、豆乳(豆漿)です。かつて上海の朝ごはん市場の半分以上を占めていたほどの人気で、今でも多くの市民に親しまれています。
これらのメニューにまつわる物語は、単なるグルメを超え、上海人の暮らしに根付いた「生活の記憶」となっています。
焼き餅(大饼dà bǐng):甘・塩あり、油条との最強コンビ!

四大金剛の一つである「大饼」には、甘いものと塩味の2種類があり、そのまま食べるだけでなく、「油条」と組み合わせて食べるのが上海流。これにはちゃんと理由があります——価格が手頃で、味の相性も抜群、そして食べやすい!という三拍子。
油条を半分に折って大餅の真ん中に挟み、大餅を二つ折りにしてパクリとひと口。「大餅+油条」が口の中でカリッと香ばしく広がる瞬間は、まさに上海の朝の味。ちなみに、使われるのは塩味の大餅が主流。というのも、甘い大餅だと折ったときに糖蜜がこぼれてしまい、食べにくいのです。
昔の「大餅」は「塌餅」だった?
実は100年前、この「大饼」は「塌饼tà bǐng」という素朴な呼び名で親しまれていました。さらに「塌饼」は、朝板(ちょうばん)、盤香(ぱんしゃん)、蟹殼黄(シエクーファン)、瓦爿(ワーピャン)などに分類されていたとか。
朝板は現在の「長大餅」、盤香はもっともポピュラーな「丸大餅」に該当。蟹殼黄は今では独自のジャンルとなり、大餅とは別の位置づけで親しまれています。

油条yóu tiáo:ハイカロリーでもやめられない、庶民の揚げパン
今日の視点で見ると「高カロリーの揚げ物」と思われがちな油条。しかし昔はこれを醤油につけて食べるだけで、ご飯のおかずにもなり得る“ごちそう”だったのです。
その起源はなんと南宋時代に遡ります。悪名高い宰相・秦檜が岳飛を殺したという伝説から、民衆は怒りを込めて小麦粉で秦檜の人形を作り、それを熱い油で揚げ、皆で噛みちぎった…というストーリーが残されています。
豆乳(豆浆dòu jiāng):上海人は「豆腐浆」とも呼ぶ
上海では豆乳のことを「豆腐浆(dòu fǔ jiāng)」と呼ぶ人も多く、淡味、塩味、甘味の3タイプがあります。
特に塩味の豆乳は中身が豊富で、細かく切った油条、干しエビ、海苔などが入り、最後に醤油を垂らして仕上げます。豆腐花(dòu fǔ huā)とも呼ばれます。

上海で最も有名だった豆乳店は「録源斎(ルーユエンザイ)」。1882年に浙江省黄岩出身の戴銭海によって創業され、豆乳に使われる大豆は東北産を厳選し、香り高くコクのある味わいが特徴。塩味の豆乳にはザーサイ、干しエビ、油条、辣油などが入っていました。
粢饭cī fàn:粢飯糕と粢飯団、似て非なるもの
「粢饭」には二つの形があります——粢饭糕(cī fàn gāo)と粢饭团(cī fàn tuán)。見た目や素材が似ていても、これはまったく別の朝食メニュー。

粢飯糕は長方形の揚げもち。外はカリッと、中はふんわり。青ネギの香りがほのかに漂い、特に四隅のカリカリ部分はやみつきになる美味しさです。

一方の粢飯団は、蒸したもち米の中に油条を丸ごと1本包んだ“ライスボール”。お店によっては白砂糖を少し加えたり、二度揚げしたカリカリの油条を使ったりすることで、香ばしさと食感がさらにアップします。食べるときは手で軽く握りながら崩れないように食べるのがコツです。
このように、「四大金剛」は単なる朝食以上に、上海人の記憶と情感が詰まった特別な存在。現代的なヘルシー志向の中でも、やっぱりたまに食べたくなる——それが上海の“朝の味”です。
上海の朝ごはんは、味だけでなく地元の生活感もたっぷり味わえる時間です。
市場の賑わいの中で、ぜひ本場の味と会話を楽しんでみてくださいね!
🚇 上海で中国語をもっと楽しもう!
もし「学んだ中国語を実際に使ってみたい」「中国人や日本人学習者と話してみたい」と思った方へ──
e-china上海校では、以下のイベントを開催しています!
🗣️ 毎週土曜10:00〜11:00
無料中国語フリートーク会(Free Talk)
どんなレベルでも大歓迎!中国語で楽しくおしゃべりしながら会話力を磨けます。
専門の中国語教師が同席して、文法や発音のサポートもしてくれます。
住所:イーチャイナアカデミー上海校 上海市长宁区古北路507号申菱大厦406室
🌏 上海で中国語を学ぶなら「イーチャイナアカデミー」!
イーチャイナアカデミーは、日本人向け中国語教育に特化した上海の中国語学校です。
名古屋本校をはじめ、20年以上の豊富な指導経験をもとに、 初心者からビジネスレベルまで確実に上達できる学習カリキュラムを提供しています。
対面レッスンに加えて、AI発音練習や会話トレーニングができる独自の eラーニング「スマチュ(smachu)」を併用することで、 「教室+スマホ」で効率的に学べるダブル学習サポートを実現。
上海生活をもっと楽しみたい方、中国語を仕事で使いたい方は、ぜひ私たちと一緒に学びましょう。
関連記事:
上海の朝ごはんは市場から!ローカルに愛される名物と使える中国語フレーズ集