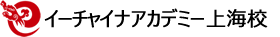上海はいよいよ毎日雨が降る梅雨の季節に入りましたね。李時珍は『本草綱目』の中で「梅雨あるいは黴雨と作し、その衣や物に触れると、皆黒いカビを出す」と述べています。この梅雨の時期に体調不良を感じる方も多いのではないでしょうか。
梅雨時の養生は、健脾化湿(脾を健やかにし、湿を取り除くこと)を主とし、食事においてはあっさりとして消化の良いものを多く摂り、胃腸を労わることが大切です。また、苦瓜や蓮子(蓮の実)など、苦味のある食材を適度に摂ることもおすすめです。これは清熱燥湿(熱を冷まし、湿を乾燥させること)の効果があるためで、まさに「苦夏(暑い夏)に苦味を食べれば、夏も苦しくない」という言葉の通りです。
ただし、冷たい飲食物の摂取は控えめにしましょう。これは腹部膨満感や下痢などの消化器症状を引き起こす可能性があるためです。
お茶は梅雨時の養生に便利な方法です。以下に、さまざまなニーズに合わせたおすすめのお茶をいくつかご紹介します。
1、健脾祛湿茶饮 (健脾祛湿茶)
枸杞茯苓茶 (クコ茯苓茶)

材料: 茯苓(ブクリョウ)10g、クコ(クコの実)5g、紅茶(紅茶)5g。
作り方: 茯苓は細かく砕いて粉末にし、その後、紅茶とクコを加えて沸騰したお湯で2回煎じ出し、お飲みください。毎日お飲みいただくことをお勧めします。
効能: 脾胃を健やかにし、腎を養う効果が期待できます。このお茶は、脾胃の機能を顕著に高め、同時に腎臓や肝臓に栄養を補給する助けとなると言われています。
禁忌: 脾胃が虚弱な方は慎重に服用してください。妊婦の方は服用を控えてください。
- 薏仁紅豆茶 (ハトムギ小豆茶)

効能: 脾胃を健やかにし、体内の余分な水分を排出する利湿作用があります。このお茶は、湿気が体質に合わない方、特に湿気が溜まりやすい方に非常に適しており、体内の余分な水分を効果的に排出するのに役立ちます。
2. 清熱解暑茶 (清熱解暑茶)
- 烏梅湯 (烏梅湯)

材料: 烏梅(うばい)50g、山査子(さんざし)30g、陳皮(ちんぴ)10g、甘草(かんぞう)30g、氷砂糖(こおりざとう)適量、桂花(金木犀)適量。
作り方: まず、烏梅をよく洗い、表面の灰を取り除きます。その後、約30分間水に浸し、弱火で40〜50分煮込みます。煮詰まったら適量の氷砂糖を加え、冷ましてからお飲みください。
効能: 津液を生み出し、喉の渇きを止める作用があります。このスープは喉の渇きを潤し、口内炎や咽頭炎などの症状を和らげるのに役立ちます。また、熱中症や過度の発汗を軽減する効果も期待できます。独特の酸味は食欲を増進させ、下痢を止める作用があり、さらに便通を促し、消化を助けることもできます。
禁忌: 脾胃が虚弱な方や胃酸過多の方は、注意して服用してください。
- 菊花枸杞茶 (菊花クコ茶)
材料: 白菊(しらぎく)適量、クコ(クコの実)適量。

作り方: 白菊とクコをコップに入れ、沸騰したお湯を注ぎ、数分蒸らしてからお飲みください。
効能: このお茶は、菊花とクコの実の特性を見事に組み合わせています。夏には体内の熱を取り除き、炎症を抑える効果があり、長時間の目の使用による眼精疲労の緩和に役立ちます。さらに、肝機能を向上させ、目を清らかにする、熱を解毒する、血圧を下げる、肺を潤して毒素を排出するなど、多くの効能が期待できます。
禁忌: 風邪による発熱時、身体に炎症や腫瘍がある方、糖尿病患者の方は服用を控えた方がよいでしょう。クコの実には糖分が多く含まれているため、糖尿病患者の方は特に注意が必要です。
- 緑豆湯/緑豆百合湯 (緑豆湯/緑豆百合湯/緑豆スープ/緑豆百合スープ)

効能: 緑豆湯または緑豆百合湯は、清熱解毒、心身の鎮静、利尿、喉の渇きを癒し、暑気を払うなど、顕著な効能があります。体の代謝機能を効果的に高めることも期待できます。
- 荷叶茶 (ハスの葉茶)

効能: 荷叶茶は夏の暑さを効果的に解消し、解熱作用と利湿作用に優れています。
3. 調理気機茶飲 (気の巡りを整えるお茶)
- 陳皮砂仁飲 (陳皮砂仁茶/チンピシャニン茶)

効能: 陳皮(チンピ)は、脾胃を健やかにし、気の巡りを整え、食欲増進や痰を取り除く効能で知られています。一方、砂仁(シャニン)には、吐き気を抑え、芳香によって湿気を和らげる作用があります。これら二つを併用することで、脾胃を温め、気の巡りを促進し、消化を助けます。このお茶は、脾胃に湿気が停滞し、気の滞りがある方、食欲不振、胸やお腹の膨満感がある方に特に適しています。 禁忌: 胃に炎症がある方、慢性的な炎症をお持ちの方、実熱証(熱が盛んな状態)の方、気血が不足している方、胃酸過多の方は、このお茶の服用を控えてください。
次回はいくつかの養生レシピをご紹介しますので、引き続きご注目ください!